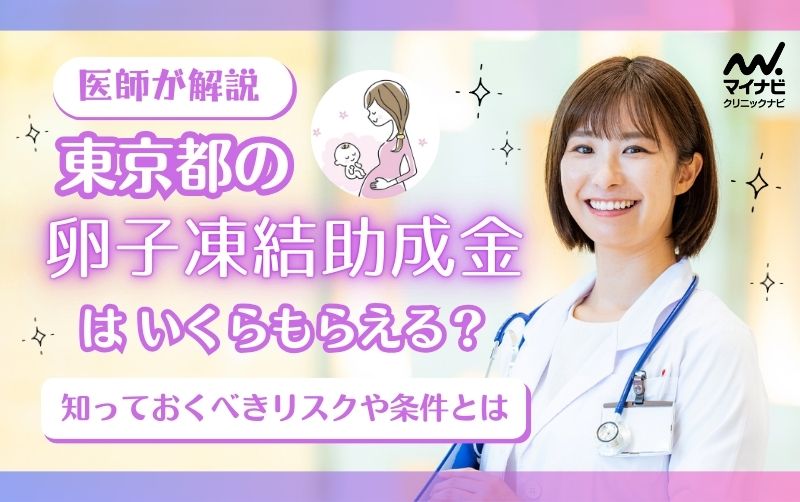晩婚化、女性の社会進出…ライフプランが多様化する現代において、将来的にども供が持てるのか、卵子の老化に不安を覚える方もいるのではないでしょうか?将来的には妊娠したいけれど、今は仕事やプライベートを優先したい。そんな女性の希望を叶えてくれるかもしれない技術、それが「卵子凍結」です。
この記事では、卵子凍結のメリット・デメリットから東京都の助成金制度、そして医療機関選びのポイントまで、あなたの将来設計に役立つ情報を網羅的に解説します。
この記事の監修者
増えている!卵子凍結への関心
近頃、テレビや雑誌で「卵子凍結」という言葉を目や耳にする機会が増えましたよね。晩婚化や女性の社会進出に伴い、卵子凍結は将来の妊娠への不安を解消する手段として、静かなブームとなっています。
最近よく聞く「卵子凍結」のメリットデメリットとは

卵子凍結とは、将来の妊娠に備えて若い時期の健康な卵子を採取し、凍結保存しておく技術です。卵子は年齢とともに変化し、その数や質に影響が出ることが分かっています。
卵子凍結は例えるなら、タイムカプセルのようなものです。大切な思い出の品をタイムカプセルに入れて保管するように、卵子凍結は若い時期の卵子を大切に保管しておく技術といえます。これにより、将来子どもを持ちたいと考えた時により多くの選択肢を持つことができます。
卵子凍結のメリット
卵子凍結には、以下のようなメリットがあります。
● 妊娠のチャンスを広げる
卵子の老化は止められませんが、凍結することで若い頃の卵子を取っておくことができます。将来、加齢によって妊娠が難しくなったとしても、若い頃の卵子があれば妊娠のチャンスを広げることができます。
● 心にゆとりが生まれる
卵子凍結をすることで、将来の妊娠への不安が軽減され、仕事やプライベートに集中できるようになります。特に、結婚や出産のタイミングをもう少し後にしたい女性にとっては、精神的な支えとなります。
● 病気の治療後も妊娠の可能性を残せる
がんなどの病気の治療は、卵巣機能に影響を及ぼし、妊娠が難しくなる場合があります。治療前に卵子を凍結保存しておくことで、治療後も妊娠の可能性を残すことができます。
卵子凍結のデメリット
一方で、卵子凍結にはデメリットやリスクも存在します。
● 費用がかかる
採卵、凍結、保管など、費用がかかります。東京都の助成金制度を利用しても、自己負担額は発生します。
● 身体への負担
排卵誘発のための注射や採卵手術など、身体への負担は避けられません。個人差はありますが、腹部の張りや痛みを感じる方もいます。
● 妊娠の保証はない
卵子凍結をしても、必ず妊娠・出産できるとは限りません。凍結卵子が融解された時の生存率は約80~95%であり、さらにその後の受精、着床、妊娠継続のプロセスを経る必要があります。
なぜ今、注目されているの?卵子凍結への関心が高まる理由

卵子凍結への関心が高まっている背景には、晩婚化や女性の社会進出、そして卵子凍結技術の進歩など、様々な要因が絡み合っています。
● 晩婚化
結婚年齢が上がるにつれ、妊娠を考える年齢も上がっています。35歳以上になると妊娠率は低下し、一方で流産率は上昇するため、晩婚化は子どもを持つことを難しくする一因となっています。
● 女性の社会進出
キャリアを築きたい女性が増え、それに伴って結婚や出産のタイミングを自分で決めたいという女性が増えています。卵子凍結は、こうした女性のライフプランをサポートする技術として注目されています。
● 不妊治療の進歩
卵子凍結技術の進歩により、卵子の生存率や妊娠率が向上しています。以前は、凍結・融解の過程で卵子がダメージを受ける可能性が高かったのですが、ガラス化法という新しい凍結方法の登場により、卵子へのダメージを極力抑えられるようになりました。
● がん治療との両立
がん治療の一部は、卵巣機能に大きな影響を与える可能性があります。卵子凍結は、がん治療を受ける女性にとって、将来の妊娠への希望をつなぐ大切な選択肢となっています。
● 東京都の助成金制度
2023年9月から東京都で卵子凍結の助成金制度がスタートしました。これにより、費用面でのハードルが下がり、東京都在住の女性は卵子凍結を検討しやすくなりました。
卵子凍結は、すべての女性にとって最適な選択ではありません。しかし、将来の妊娠について悩んでいる方にとっては、選択肢を広げる一つの方法です。メリット・デメリット、費用、リスクなどをよく理解した上で、自身のライフプランに合わせて慎重に検討することが大切です。
卵子凍結って実際どんなもの?
続いて、卵子凍結についてより詳しく解説していきたいと思います。
卵子凍結の基礎知識

卵子は、女性が生まれた時から卵巣の中に存在し、年齢とともに数が減少し、質も低下していきます。卵子の老化は20代後半から始まり、35歳頃から妊娠率は徐々に低下し始め、40歳を過ぎるとさらに急激に低下すると言われています。
卵子凍結は、大きく分けて「社会的適応」と「医学的適応」の2つのケースで行われます。社会的適応とは、仕事やプライベートの都合で、今は妊娠・出産できないけれど、将来子どもを持ちたいという場合です。医学的適応とは、例えばがん治療などの医療行為によって卵巣機能が低下する可能性がある場合に、将来の妊娠に備えて卵子を保存しておく場合です。
誰が受けられる?費用はどのくらい?

卵子凍結は、基本的に健康な女性であれば誰でも受けることができます。ただし、日本生殖医学会のガイドラインでは採卵時の推奨年齢は40歳未満、凍結卵子の使用時の推奨年齢は45歳未満(44歳まで)となっています。このガイドラインの推奨を踏まえて、クリニックでは年齢制限を設けている場合もあります。
費用はクリニックや採卵する個数によって異なりますが、一般的には採卵、凍結、保管などを含めて40万円程度かかります。その内訳は、初診および各種術前検査に3〜4万円、排卵誘発および採卵に20〜35万円、卵子凍結前処理に1万円、凍結卵子の保管に年間5〜15万円(個数による) となっています。
費用を抑えたいという方は、東京都の助成金制度の利用を検討してみましょう。助成金制度を利用することで、費用面でのハードルが下がり、卵子凍結を検討しやすくなります。
実際の流れ

卵子凍結は、いくつかのステップを経て行われます。
1.事前検査
まずは、血液検査や超音波検査などを行い、卵巣の状態やホルモン値などを確認する事前検査から始まります。
2.排卵誘発
次に、排卵誘発を行います。注射や内服薬を使って、複数の卵胞を育てます。卵子は通常1回の生理周期で1~2個しか排卵されませんが、卵子凍結では一度に複数の卵子を採取するため、排卵誘発剤を用いて卵胞を育てます。
3.採卵
その後、採卵を行います。膣から針を刺し、卵巣から卵子を採取します。所要時間は10分程度で、静脈麻酔を使う場合もあります。クリニックによっては、身体への負担が少ない局部麻酔を採用しているところもあります。
4.凍結
最後に、採取した卵子を液体窒素を使って凍結保存します。凍結保存された卵子は、将来、妊娠を希望する時に融解して使用することができます。
卵子凍結は、体外受精と同様に、身体的・精神的な負担を伴う治療です。また、卵子凍結を行っても、必ずその卵子で妊娠・出産できるという保証はありません。卵子の融解後の生存率は80~95%程度で、さらにその後の受精、着床、妊娠継続のプロセスを経る必要があります。
東京都の卵子凍結助成制度
東京都の卵子凍結助成制度は、卵子凍結を活用して、将来の妊娠の可能性を広げるための経済的なサポートを提供するものです。女性の社会進出が当たり前になった現代において、妊娠・出産のタイミングをコントロールすることは、多くの女性にとって重要な課題となっています。東京都の助成制度は、そんな女性たちのライフプランを支援し、安心して将来設計を描けるようにすることを目的としています。
助成金の概要

東京都の卵子凍結助成制度は、卵子凍結に係る費用と、凍結卵子を用いた生殖補助医療に係る費用の2つを助成対象としています。
卵子凍結に係る費用
卵子凍結に係る費用の助成は、採卵準備のための投薬から採卵、そして卵子の凍結までの費用が対象で、上限20万円が助成されます。
さらに、凍結卵子を保管している間、東京都の調査に協力することで、保管費用として年間2万円(最大5年間)の追加助成を受けることができます。つまり、最大で合計30万円もの助成を受けることができるのです。
凍結卵子を用いた生殖補助医療に係る費用
凍結卵子を用いた生殖補助医療の助成は、凍結しておいた卵子を使って体外受精や顕微授精などの生殖補助医療を受ける際にかかる費用が対象です。助成額は1回につき上限25万円で、最大6回まで助成を受けることができます。
申請に必要な条件は?

助成を受けるためには、いくつかの条件があります。それぞれの助成で条件が異なるため、注意が必要です。
卵子凍結に係る費用への助成を受けるには
・東京都在住
・18歳から39歳までの女性(採卵を実施した日における年齢)
・都が開催する説明会に参加
・都が指定する登録医療機関で治療を受けるなど
東京都に住んでいる18歳から39歳までの女性であること、都が開催する説明会に参加すること、そして都が指定する登録医療機関で治療を受けることが必要です。さらに、卵子凍結後も都の調査に協力することが求められます。
上記のような条件を満たしても、必ずしもすべての人が対象となるわけではありません。例えば、すでに不妊治療を受けている方や、がん治療などで生殖機能温存治療を受けている方は、東京都の助成金制度の対象外となる場合があります。
凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成を受けるには
・夫婦(事実婚を含む)
・妻の年齢が43歳未満(生殖補助医療の開始時点での年齢)
・夫婦いずれか(事実婚の場合は両方)が都内に住民登録
・都が指定する登録医療機関で治療を受けるなど
夫婦(事実婚を含む)で、妻の年齢が43歳未満であること、夫婦いずれか(事実婚の場合は両方)が都内に住民登録をしていること、そして都が指定する医療機関で治療を受けることなどが条件となります。
具体的な申請方法と必要書類

助成金の申請は、原則として電子申請で行います。東京都の福祉保健局のホームページから申請フォームにアクセスし、必要事項を入力します。マイナンバーカードが必要となるため、事前に準備しておきましょう。もしマイナンバーカードを持っていない場合は、メールで東京都福祉保健局とやり取りすることになります。
申請に必要な書類は、住民票の写し、説明会参加証明書、医療機関の領収書などです。詳しい必要書類や申請方法は、東京都福祉保健局のホームページで確認できますので、必ず自身で最新の情報を確認するようにしましょう。
申請期限は、卵子凍結を実施した年度によって異なりますので、注意が必要です。助成金の支給は、申請後1ヵ月程度かかります。
また、助成金は1人につき1回限りです。ご自身の状況に合わせて、しっかりと制度の内容を理解し、利用を検討することが大切です。
医療機関選びのポイント
卵子凍結は、将来の妊娠に向けて大切な卵子を保管する技術です。将来の選択肢を広げるためにも、信頼できる医療機関選びが非常に重要になります。自分に合った医療機関を見つけることは、安心して治療を受けるための大きな一歩です。
この章では、医療機関を選ぶ際に特に注目すべきポイントを、医師の視点も交えながら詳しく解説します。
病院選びで確認したい4つのこと

卵子凍結を行う医療機関を選ぶ際には、以下の5つのポイントを参考にしましょう。
1. 実績と経験
卵子凍結の実績が豊富で、経験を持つ医師が在籍している医療機関を選びましょう。実績が多いということは、それだけ多くの症例を経験し、様々なケースに対応できるノウハウが蓄積されている可能性が高いことを意味します。
ホームページや口コミサイトなどで、実績や症例数を確認するだけでなく、医師の経歴も参考にすると良いでしょう。例えば、日本産科婦人科学会専門医の資格を持っているか、生殖医療専門医の資格を持っているかなども、重要な指標となります。
2. 費用
卵子凍結は自由診療のため、医療機関によって費用が大きく異なります。東京都の助成金制度を利用する場合でも、助成対象医療機関であるかどうかの確認は必須です。助成対象医療機関であれば、費用の一部が助成されるため、経済的な負担を軽減できます。
可能であれば複数の医療機関で見積もりを取り、費用を比較検討することが大切です。費用面だけでなく、費用に含まれる内容(例えば、採卵費用、凍結費用、保管費用、診察費用、薬剤費用など)も確認しておきましょう。
3. サポート体制
卵子凍結は、身体的にも精神的にも負担がかかる治療です。安心して治療に臨めるよう、親身になって相談に乗ってくれる医療機関を選びましょう。
カウンセリング体制が整っているか、看護師やスタッフの対応は丁寧かなど、サポート体制も重要なポイントです。治療中の不安や疑問を気軽に相談できる環境が、治療を続けるうえで大きな支えとなります。
4. アクセス
通院しやすい場所にある医療機関を選ぶことも、治療をスムーズに進める上で大切な要素です。治療期間中は、定期的に通院する必要があるので、自宅や職場から近い医療機関だと、通院の負担を軽減できます。
特に、排卵誘発中は、卵胞の成長に合わせて複数回の通院が必要となる場合もあります。通院の負担を最小限にするためにも、アクセスの良さを考慮に入れて医療機関を選びましょう。
実際に通院する際の注意点

医療機関が決まったら、実際に通院する際の注意点も確認しておきましょう。
1. 初診時の問診と検査
初診時には、問診や血液検査、卵巣機能検査(AMH検査など)など、様々な検査が行われます。過去の病歴やアレルギーの有無、現在の服用薬など、正確な情報を伝えるようにしましょう。医師から説明を受ける際には、疑問点があればメモしておき、その場で質問するようにしましょう。
また、卵子凍結を行う理由や将来の妊娠に対する希望なども、医師に伝えておくと、より適切なアドバイスを受けることができます。
2. 排卵誘発
卵子を採取するために、排卵誘発剤を使用します。注射や内服薬など、患者の状況に合わせた方法を選びます。排卵誘発剤を使用することで、通常1回の生理周期で1~2個しか排卵されない卵子を、複数個同時に成熟させることができます。
副作用として、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などのリスクも存在するため、医師とよく相談し、適切な方法を選択することが重要です。副作用の症状や対処法についても、事前に確認しておきましょう。
3. 採卵
卵巣から卵子を採取する手術です。手術には麻酔を使用することがあるため、術後の回復時間や日常生活への影響について、医師に確認しておきましょう。手術当日は、食事制限や飲水制限があるので、指示に従いましょう。採卵は、膣から針を刺して卵胞を吸引する方法で行われます。所要時間は10分程度です。
4. 凍結保存
採取した卵子は、液体窒素を用いたガラス化法で凍結保存されます。凍結保存された卵子は、理論上、半永久的に保存することが可能です。保管期間や保管方法、保管費用について、医療機関に確認しておきましょう。
5. 費用と支払い方法
医療機関によって費用や支払い方法が異なるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。分割払いやクレジットカード払いが可能かなども、確認しておくと便利です。
また、東京都の助成制度を利用する場合は、申請方法や必要書類なども確認しておきましょう。
これらのポイントを参考に、ご自身に最適な医療機関を選び、安心して卵子凍結に臨んでください。
おわりに:これからのライフプランを考える

人生における様々なライフイベント、例えば結婚、出産、就職、転職、昇進などは、人それぞれ異なるタイミングで訪れ、その優先順位も様々です。しかし、妊娠・出産は、年齢とともに身体的な負担が増加するだけでなく、妊娠自体が難しくなることもあります。将来子どもを望む方々にとって、これは大きな不安要素となるでしょう。だからこそ、卵子凍結という選択肢を知っておくことで、心にゆとりが生まれる可能性があります。
卵子凍結がすべての女性にとって最適解ではありませんが、将来の妊娠に悩む女性にとって、選択肢を広げてくれる有効な手段です。情報を集め、自分自身の価値観やライフプランと照らし合わせながら、卵子凍結についてじっくりと検討してみてください。本記事がその一助となれば幸いです。
(監修・執筆:丸山潤)
参考文献
1. Chang CC, Shapiro DB, Nagy ZP. The effects of vitrification on oocyte quality. Biology of reproduction 106, no. 2 (2022): 316-327.
2.みんなで一緒に知りたい卵子凍結のこと(卵子凍結の手引). 東京都福祉局.
3.卵子凍結に係る費用の助成. 東京都福祉局.
※画像はイメージです
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。