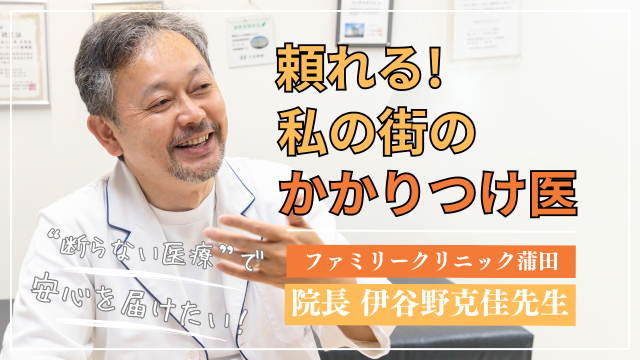高齢化が進む日本では、団塊世代が現役を退く2025年問題など、多くの課題があります。厚生労働省の資料によると、2025年には29万人が在宅医療を必要とすると試算されており、終末期ケアも含む生活の質を重視した 医療としての在宅医療のニーズは大きく高まっています。
今回は、医療法人社団双愛会理事長でファミリークリニック蒲田院長の伊谷野克佳先生にお話を伺いました。外科医 として病院で診療をしてきた伊谷野先生が、訪問診療を始めた理由には「安心を提供したい」という、一人の医師としての強い思いがありました。
お話を聞いたのは
訪問診療を始めたのは「専門性を極めるよりも広い視野で医療と向き合いたい」との思いから
――先生は訪問診療クリニックを開業してから約20年と、長い間地域医療に貢献されてきましたが、なぜ訪問診療を始めようと思ったのでしょうか?

私は大学卒業後に大学病院で外科医として手術などの臨床を行ってきました。大学病院で働いていた頃は、他の診療科で手術が必要と判断されると外科に紹介され手術を行っていました。手術が無事終われば患者さんは退院していきます。私は外科医として、患者さんと手術の期間しか関わることができず、言い方は良くないですが、どうしても“流れ作業”のような形になってしまう仕組みがありました。
また、医師はキャリアを積めば積むほど専門領域が狭くなっていくんです。私の場合は、最初は外科に入り、その後胸部領域を専門に進み、さらには心臓・血管に進んでいきました。もちろんスペシャリストとしての経験や技術は向上していくので素晴らしいことではあります。ただ、私が医者になったきっかけに、「色々な人の役に立ちたい」という思いがあったんです。専門性を高めていくとそれ以外のことが分からない医師が少なくない状況を見てきて、なんのために医者になったのかと、自分なりに考えることがありました。
そうした中でたどり着いた1つの答えが、訪問診療でした。訪問診療は医学的な知識、技術はもちろん必要とされていますが、あくまでもその患者や家族の状況に合わせてコーディネートしています。個人的には、どちらかというと全体的にコーディネイトしながらやっていく方が、性に合っていました。専門性を極めるよりも広い視野でできた方が私にとっては価値があったのです。
そうした気持ちになり始めたのと同じタイミングで、介護保険が2000年にできました。この制度が私の背中を押す材料にもなり、2005年から少しずつ在宅医療を始めました。
病院の医師と訪問診療の医師の違い
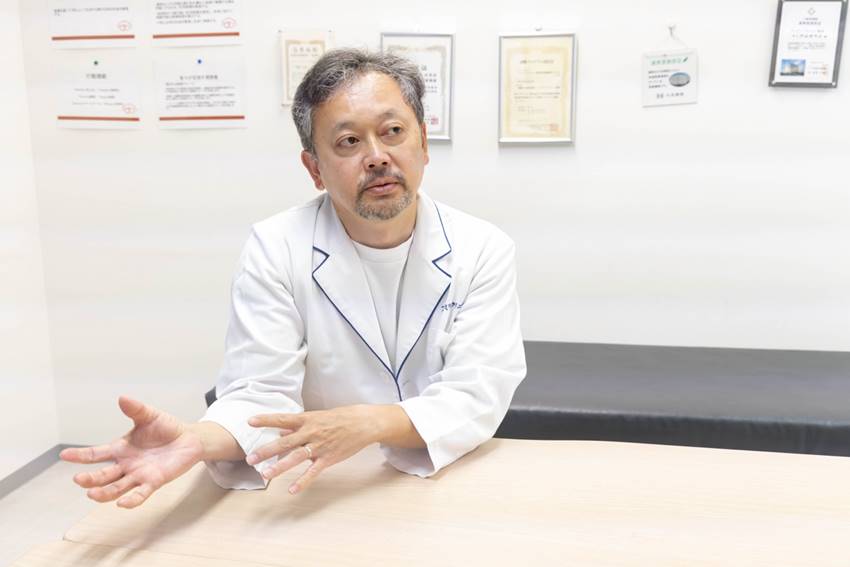
――先生の気持ちと国の制度設計がうまく重なったのですね。病院の医師と訪問診療の医師では求められるものは違うのでしょうか?
違うと思いますね。大学病院の医師は患者さんに対して仮に不愛想であったり、クールなタイプだったとしても、医学的に正しく腕がいい医師が正しいと思います。一方で、訪問診療を行う医師に求められることは、医学的に正しいことや腕の良さももちろん必要ですが、それよりも科学ではない部分、いわゆる患者さんや家族の希望や背景を考慮しながらベストな答えをお互いに擦り合わせていくことが求められます。
医学的な正しさと、患者さんや家族の希望の、どちらか一方に偏ってもベストな結果にはならないと思っていますので、しっかりとコミュニケーションをとりながら進めていくことが必要です。これまで20年ほど訪問診療を行っていますが、患者さんや家族から満足してもらうことが多いので、私はきっと得意な方なのだと思いますね。
――確かに、先生とお話ししているとリラックスして話が進みます。きっと患者さんも同じような気持ちになるのでしょうね。
ファミリークリニック蒲田の得意分野は?

――訪問診療ではどのような在宅医療を提供しているのですか?
私たちのクリニックは、自宅で療養していて体が不自由で通院が難しい患者さんや、病院での入院治療が終わって最終的に自宅療養でと言われる患者さんの自宅に訪問しています。
病気を持たれた状況で自宅療養をすることがメインなので、患者さんの状態を観察し、血液検査を自宅で行なったり、病状変化した時に自宅で応急処置をしています。
――クリニックとして力を入れている領域はあるのでしょうか?
クリニックで力を入れているのは緩和ケアでしょうか。がんなどの病気があって、治療が終了し、最終的な終末期を痛みのコントロールなどをしながら自宅で過ごす人は意外と多いのです。私たちのクリニックの患者さんの中の割合は、おそらく他のクリニックに比べると緩和ケアの患者さんの割合は多いと思います。ただ、クリニックとして緩和ケアがやりたくで始めたのではなく、「断らない医療」を推し進めた結果として、緩和ケアの患者さんが増えたのかと思っています。
緩和ケア以外ですと、メンタルヘルス、認知症には力を入れていますね。また、私たち独自の救急センターにも力を入れています。
患者さんと接するときに心がけていることは「断らない」姿勢
――先生が患者さんやご家族とのコミュニケーションをとる際に心がけていることは何ですか?
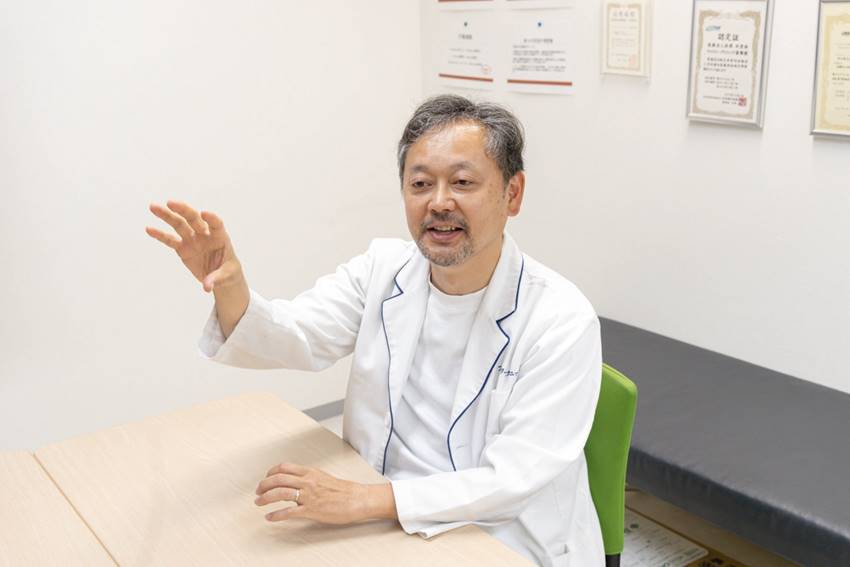
私たちのクリニックは、「断らない医療」という合言葉でやってきました。紹介を受けたら基本的にはお受けし、私たちが対応できる範囲でベストな医療を提供することを心がけています。
私は患者さんに必ず最初に「どのような生活をしたいですか?」と聞くようにしています。例えば余命が3〜6カ月と言われて帰ってきた患者さんに対して、残された時間を自宅でどう過ごしたいと考えているかを知ることはとても重要です。しかしながら、患者さんや家族は、ご自身が希望する生活が「どうせ無理なんでしょ」と、考えてしまい半分諦めている人が多いんです。
ですから、私がお会いする前に頭にインプットしたものを一回取っ払うということが必要になります。患者さん本人だったり、両親、遠方に暮らしている家族だったりがどう過ごしたいか、余計な先入観なしに希望を話してもらうのです。その意見を受けて、私たちのクリニックの体制で出来ることと出来ないことを伝えます。
――出来ないことを正直に伝えることは勇気がいることでもあると思いますが、大事なことなのですね。
そうですね。医療に携わる人たちって基本的に“良い人”が多いと思います。ですから、患者さんの希望に対して、普通であれば出来ないことでも無理をして頑張ってやろうとしてしまいます。ところが、ここで無理すると続かなくなってしまうんです。私たちは1人の患者さんだけ診れば良いというわけにはいきません。多くの方の健康を預かっています。特定の患者さんで無理をすると、他の患者さんに本来かけるべきリソースを削ることになってしまいます。クリニックとして無理がない範囲で、でも患者さんにとってのベストを尽くすことが重要です。
チーム体制発足のきっかけは伊勢谷先生の声がストレスで出なくなったから
――地域にいらっしゃる多くの患者さんの健康の責任を持っている立場だからこそ、無理をしてはいけないのですね。こうした考えに至るきっかけはあったのでしょうか?

無理をしないという考えは、私自身の経験によるものですね。このファミリークリニック蒲田は、私がたった1人で始めました。何をするにも初めての経験ばかりで忙しかったのですが、大学病院の外科も相当忙しかったので、それに比べると問題ないと思っていました。
しかし開業してから1年半くらい経つと、忙しすぎてろれつが回らなくなりうまく言葉が出なくなってしまったんです。昼も夜間コールも1人で対応していましたから、今から思うと相当無理をしていましたね。そこで、当時「これはまずいと」と思い、仕事の量を減らして自分1人でできる範囲で医療を提供していくかチームを作って体制を構築するかを真剣に考えました。
考えている中で1つ発見したのは、どれだけ規模を小さくしても在宅医療を提供する限りは24時間体制を維持する必要があるということです。ここに理解が及ぶと、そもそも規模を減らしても無理な体制は解決できないとわかり、そこからチームを作りに舵を切りました。

多くの試行錯誤を経て、現在では無理がない形で24時間医療を提供できる仕組みができ、3拠点に100人のスタッフを抱えるまでにチームが成長しました。
――声が出なくなってしまうのでは、衝撃的ですね・・・息抜きなども出来ていなかったのでしょうか?
そうですね、今から思うと色々と自分で制約をかけていましたね。私は元々旅行が趣味だったのですが、クリニックを開業してからしばらくは旅行に行くことを封印していました。
――好きなことが出来ないのは、ストレスも溜まりそうですね。今では、息抜きは出来ているんですか?
そうですね、アクティビティは結構やっていますよ。そのためクリニックで課外活動を支援しています。登山が趣味のスタッフを筆頭に登山部を結成して山登りに行ったり、サーフィンが好きなスタッフで海(うみ)部を結成して波乗りに行ったりしています。最近球技部も活動開始しました。ちなみに私は自然が好きなので、山と海に行きますよ。
――クリニックの皆さんも仲がいいんですね。医療にチームワークは欠かせないと思うので、こうしたスタッフ同士の関係性の良さはとても魅力的です。ちなみに3拠点もあるとのことですが、普段の情報共有はどのようにしているのでしょうか?

電話やメールなどももちろん使いますが、実は私たちのクリニックでは、新型コロナの流行前からオンライン会議を実施しているんです。カンファと呼ばれる、患者さんの状況などを確認するための定例会議は各拠点を繋いでオンラインで行います。
元々オンラインを活用していたので、新型コロナで世の中がオンライン対応で大変な状況になっていても、私たちのクリニックはスムーズに体制維持をすることができました。
――新しい仕組みを取り入れることに抵抗がないのは素晴らしいですね。
「地域全体で無理のない在宅医療の救急体制を作りたい」
――すでに素晴らしい組織である先生のクリニックの展望を教えてください。
もうすでに動き出しているのですが、これまで私たちのクリニックの重要な柱の1つとしてきた在宅救急センターを他の在宅クリニックにも利用してもらえるように外部開放を開始しました。この活動によりこの地域全体が安心できる社会を作りたいと考えています。
地域全体にコミットしようとすると、私たちのクリニックだけだと足りません。ですから、他のクリニックでもぜひ利用してもらい、地域全体で無理なく医療体制を充実させていきたいと思っています。
私は自分自身がうまく言葉が出なくなるほど無理をした経験から、今の体制や仕組みを構築しました。地域には現在も1人でも24時間頑張っている先生もいらっしゃるので、ぜひご活用いただき、無理ない診療体制作りの一助にしていただきたいです。
――地域全体の医療体制を無理なく充実させる、という思いは素晴らしいですね。今後の展開が楽しみです。
受診を検討している患者さんへのメッセージ
――最後に、受診を検討している患者さんや家族へのメッセージをお願いします。
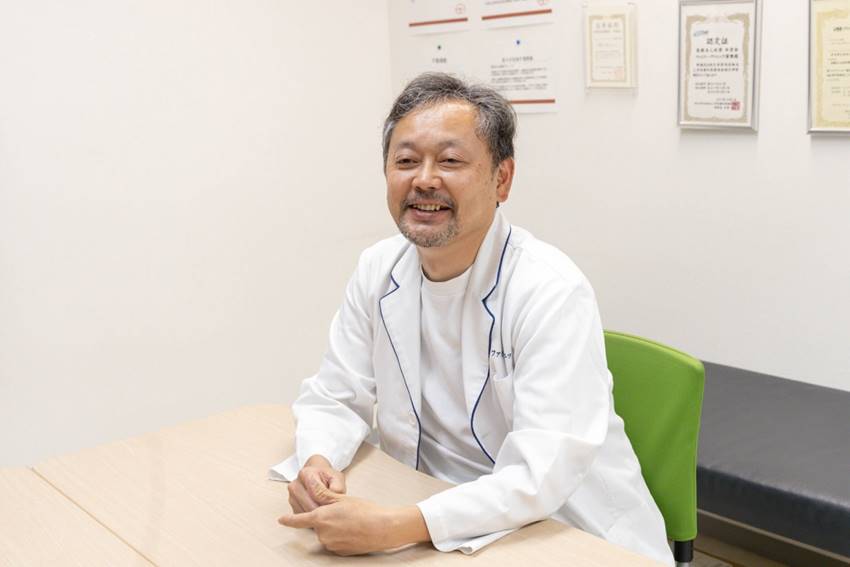
我々は訪問診療と通じて「安心」を提供しています。安心して生活できることは社会のインフラだと思います。蛇口をひねるときれいな安心するお水が出るのと同じように、病気になっても安心して生活できる地域を作っていきたいと考えています。
ご自宅でどうやって過ごしていきたいかを遠慮なく教えてください。無理かなと思っても、もしかしたら簡単にできるかもしれないし、工夫したら叶うかもしれません。まずは私たちにお話をお聞かせください。
――伊谷野先生にお話を伺った際の第一印象は、自然体が素敵な先生だな、ということでした。インタビューが進むにつれて訪問診療に対する熱意を身振り手振りを交えながら教えていただき、こうした先生が地域にいることが地域医療にとっては大変重要なことだと感じました。先生はベン・スティラーが主演を務めた『LIFE!/ライフ』がお気に入りの映画だと教えていただきましたが、奇遇にも筆者の好きな映画でもありました。先生も筆者も『LIFE!/ライフ』について語り合える相手がなかなかいなかったのでインタビュー中にも関わらず盛り上がってしまいました。先生のトレードマークのヒゲは『LIFE!/ライフ』の登場人物に憧れて生やしているそうです。チャーミングな一面も持つ先生の、これからのご活躍が楽しみです。
(取材:メディコレ編集部)